4月の琵琶湖でのバス釣り攻略は、スポーニング(産卵)行動を理解し、状況に合わせたルアー選択が釣果を分ける鍵となります。
この記事では、琵琶湖で4月に実績のあるおすすめバス釣り ルアー10選や、おかっぱり・ボートなどの状況別攻略法、プリスポーン期のバスを狙うコツを解説しますので、次回の釣行でデカバスをゲットする確率を高められます。
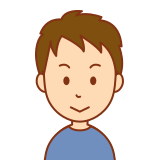
春の琵琶湖、どんなルアーを使えば釣れるんだろう…?

2025年最新!4月の琵琶湖で実績のあるルアーと攻略法を詳しく解説しますよ
- 4月の琵琶湖バスの行動(スポーニング期)とルアー選択の重要性
- 2025年版 おすすめルアー10選と具体的な使い方
- 南湖・北湖・おかっぱり・ボートなど状況に応じたルアー戦略
- 春の琵琶湖攻略のための準備と安全な楽しみ方
4月の琵琶湖バス攻略の鍵 スポーニング期のルアー選び
4月の琵琶湖でバスを攻略する上で、最も重要なのはスポーニング(産卵)行動を理解し、それに合わせたルアーを選ぶことです。
この時期特有のバスの動き、特に産卵前のプリスポーン期の状態や、水温・天候の変化にどう対応するかが、ルアー選択を通じて釣果に直結します。
正しい知識に基づいたルアー選びで、春のデカバスゲットの確率を高めましょう。
春の琵琶湖バスの行動 スポーニングとは
スポーニングとは、魚類の「産卵行動」を指す言葉です。
バス釣りにおいては、特に春の重要なキーワードとなります。
4月の琵琶湖では、バスは冬の深場から水温が10度を超え始めると浅場(シャロー)へ移動し、産卵に適した場所(スポーニングベッド)を探し始めます。
この行動が釣りの戦略に大きく影響しますよ。
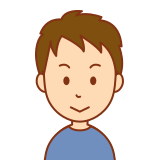
スポーニングって、具体的にバスはどうなるんですか?

産卵前は体力をつけるために荒食いしたり、逆に神経質になったり、産卵中はオスが巣を守ったりと、行動が複雑化しますね
スポーニングの一連の流れを把握することが、春バス攻略の第一歩です。
プリスポーン攻略の重要性
プリスポーンとは、スポーニング(産卵)前の時期を指し、バスが体力を蓄えるために積極的にエサを追う期間です。
この時期のメスバスは栄養を蓄えようと、大型のベイトフィッシュ(小魚)を捕食する傾向があり、比較的ルアーへの反応が良いことが多いです。
適切なルアーを使えば、一年で最も大型のバスをキャッチできるチャンスが高まります。
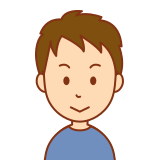
プリスポーンのバスは釣りやすいってことですか?

比較的釣りやすい時期ですが、状況変化に敏感なので油断は禁物ですよ
プリスポーンのバスの居場所と捕食スイッチを見極めることが、4月の琵琶湖攻略には不可欠です。
なぜルアー選択が釣果を左右するのか
スポーニング期のバスは、通常時とは異なる行動パターンを示すため、その状況にマッチしたルアー選択が釣果を大きく左右します。
例えば、産卵を意識して神経質になっているメスには静かにアピールするワームが有効な場合もあれば、縄張り意識の強いオスには威嚇バイトを誘う派手な動きのルアーが効くこともあります。
このように、バスの状態や狙いに合わせてルアーを使い分ける必要があります。
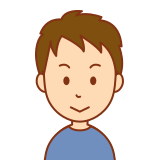
いつも同じルアーばかり投げちゃいます…

バスの反応を見ながら、ルアーの種類やカラー、動かし方を変えていくのが重要です
ルアーが持つ特性(動き、波動、色、レンジ)を理解し、戦略的に投入することが、気難しい春バスを攻略する鍵です。
水温と天候変化への対応
春の琵琶湖は「三寒四温」と言われるように、日々の水温変化が大きいのが特徴です。
この変化がバスの活性に直接影響します。
例えば、暖かい日が続いて水温が上昇傾向にあればバスの活性は上がり、動きの速いルアー(バイブレーションやスピナーベイト)にも反応しやすくなります。
逆に、冷たい雨などで水温が急低下した場合は活性が下がり、ゆっくりと誘えるルアー(サスペンドミノーやネコリグ)が有効になります。
| 状況 | バス活性 | 有効なルアータイプ例 |
|---|---|---|
| 水温上昇・晴天 | 高 | バイブレーション、スピナーベイト |
| 水温安定・曇天 | 中 | ミノー、シャッド、クランクベイト |
| 水温低下・雨天 | 低 | サスペンドミノー、ネコリグ、シャッド |
天気予報や現地の水温を常にチェックし、その日の状況に合わせたルアー選択とアプローチを心がけることが重要です。
4月の琵琶湖で実績あり おすすめルアー10選とその使い方
- プリスポーンのメス狙い サスペンドミノー
- 低水温・高プレッシャーに シャッド
- 広範囲サーチとリアクション狙い バイブレーション
- ウィード攻略の定番 スピナーベイト
- ボトム攻略の切り札 クランクベイト
- 食わせの定番 ネコリグ
- 中層ふわふわ誘い ジグヘッドワッキー
- カバー撃ちの静かな一手 高比重ワーム
- おすすめルアーの使い方 アクションの基本
- 実績カラーの選び方 ナチュラル系とアピール系
4月の琵琶湖でバス釣りの釣果を上げるためには、スポーニング(産卵)を強く意識したルアー選びが何よりも重要です。
この時期のバス、特にプリスポーン(産卵前)のメスや、産卵床を守るオスは、普段とは異なる行動を見せます。
サスペンドミノーで中層を漂うプリスポーンのメスを狙ったり、シャッドで低水温や高プレッシャー下のバスに口を使わせたり、バイブレーションで広範囲を探りリアクションバイトを誘発したりすることが有効です。
また、ウィードエリアではスピナーベイト、ボトム付近ではクランクベイトが活躍します。
食いが渋い状況では、ネコリグやジグヘッドワッキー、高比重ワームといった「食わせ」のルアーが頼りになります。
これらのルアーの基本的な使い方(アクション)や、状況に応じたカラーの選び方を理解することも釣果に繋がります。
それぞれのルアーの特徴を把握し、琵琶湖の状況に合わせて使い分けることで、春のデカバスとの出会いをぐっと引き寄せることが可能になります。
プリスポーンのメス狙い サスペンドミノー
プリスポーン期のメスバスは、産卵に備えて体力を蓄えるため、特定のレンジ(水深)でベイトフィッシュを待ち構えていることが多いです。
そんなバスに効果的なのが、一定の水深で停止(サスペンド)させることができるサスペンドミノーです。
ジャークやトゥイッチでルアーを左右にダートさせ、その後のポーズ中にバイトを誘発するのが基本テクニックとなります。
特に水温が低い朝マズメや夕マズメ、日中の活性が低い時間帯に、3秒~10秒程度の長めのポーズを入れると効果的です。
| おすすめルアー | 特徴 | 推奨カラー例 |
|---|---|---|
| O.S.P 阿修羅 SP | キレのあるダートアクションと安定したサスペンド | ゴーストアユ、リアルワカサギ |
| メガバス VISION ONETEN | 独特な水中姿勢と強いフラッシング | GP プロブルー、マットタイガー |
| ジャッカル リレンジ110SP | 優れた飛距離とリアルなスイムアクション | HLワカサギ、チャートバックパール |
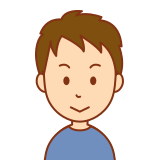
どんな時にポーズ時間を長くすればいいの?

水温が低い時や、バスの反応が鈍いと感じる時に長めに止めてみてください
狙う水深に合わせて、ルアーのリップ形状(ロングビル、ショートビルなど)を選ぶことが、釣果への近道となります。
低水温・高プレッシャーに シャッド
シャッドは、ミノーに比べてよりタイト(細かい)でナチュラルな動きが特徴のルアーです。
そのため、4月初期の低水温でバスの動きが鈍い時や、連日の釣行でプレッシャーが高くなっている状況でも、バスに違和感を与えにくく、口を使わせる能力に長けています。
基本はただ巻きですが、時折軽いトゥイッチを加えて、ルアーの動きに変化を与えるとリアクションバイトを誘発しやすくなります。
琵琶湖で多いウィードエリアでは、ウィードの少し上(ウィードトップ)をかすめるように、1.5m~2.5m程度のレンジを引いてくるのがおすすめです。
| おすすめルアー | 特徴 | 推奨カラー例 |
|---|---|---|
| ジャッカル ソウルシャッド | 高速リトリーブでも安定した泳ぎ、鋭いダート | HLワカサギ、ゴーストワカサギ |
| レイドジャパン レベルシャッド | スローリトリーブでの安定性と細かいピッチ | シマナシタイガー、パールシャッド |
| エバーグリーン スーパースレッジ | 低活性バスに効く微細なアクション | ナチュラルワカサギ、マジワカ |
繊細なバイト(アタリ)も多いルアーなので、フロロカーボンラインなどの感度の良いラインシステムを組むことを推奨します。
広範囲サーチとリアクション狙い バイブレーション
春の広大な琵琶湖で、バスがどこにいるか効率的に探したい場合に最も適したルアーの一つがバイブレーションです。
その強い波動(ブルブルという振動)と、ボディ側面でのフラッシング(光の反射)は、遠くにいるバスにも存在を気づかせ、引き寄せる力があります。
ただ巻きによる広範囲サーチはもちろん、春の琵琶湖ではリフト&フォール(竿をしゃくり上げてルアーを持ち上げ、その後カーブフォールさせる動作)が非常に効果的です。
この動きで、バスのリアクションバイト(反射的な食いつき)を誘います。
特に水温が上がり始める日中や、風が吹いて湖流が発生したタイミングで試してみてください。
3m~5mといったやや深めのレンジ攻略にも向いています。
| おすすめルアー | 特徴 | 推奨カラー例 |
|---|---|---|
| エバーグリーン リトルマックス | コンパクトボディながら強い波動と飛距離 | プリスポーンダイナマイト、キンクロ |
| デプス サーキットバイブ | 早いリフトでもバランスを崩しにくい設計 | ブルーギル、レッドギル |
| レイドジャパン レベルバイブ | 喰わせ能力の高いタイトなアクション | シッコクタイガー、ピンクバックタイガー |
根掛かりが多いルアーでもあるため、ボトムの地形やウィードの有無を把握しながら、リフトの高さを調整することが大切です。
ウィード攻略の定番 スピナーベイト
4月の琵琶湖、特に南湖エリアで重要となるのがウィード(水草)の存在です。
プリスポーンのバスが身を寄せたり、フィーディング(捕食)したりする格好の場所となります。
そんなウィードエリアを攻略する上で欠かせないのがスピナーベイトです。
ワイヤーアーム構造により、ウィードへの根掛かりが少なく、ストレスなく攻めることができます。
ブレード(金属板)が回転することで発生するフラッシングと波動が、バスへの強いアピールとなります。
ウィードにわざと軽く接触させながらゆっくり巻く「スローロール」や、ウィードを抜けた瞬間のバイトを狙うのが効果的です。
ブレードの形状(コロラド、ウィローリーフ)や枚数(シングル、タンデム、ダブル)でアピール力を調整できるため、状況に合わせて使い分けましょう。
1/2oz(約14g)前後のウェイトが基準となります。
| おすすめルアー | 特徴 | 推奨ブレードタイプ/カラー例 |
|---|---|---|
| O.S.P ハイピッチャー | コンパクトながら強いバイブレーションと立ち上がりの良さ | タンデムウィロー/ゴールド、シルバー |
| デプス Bカスタム | スナッグレス性能が高く、ビッグバス対応 | ダブルウィロー/チャート、ホワイト |
| ノリーズ クリスタルS | 多彩なブレードコンビネーションと安定した泳ぎ | タンデムウィロー/ワカサギ、アユ |
ショートバイトが多いと感じる場合は、トレーラーフックを装着することでフッキング率を高めることができます。
ボトム攻略の切り札 クランクベイト
クランクベイトは、リップと呼ばれる先端部分で潜行深度が決まり、ボトム(湖底)やハードストラクチャー(岩、杭など)にコンタクト(接触)させてリアクションバイトを狙うのに適したルアーです。
プリスポーンのバスが付きやすいとされる硬い底(ハードボトム)や、浚渫(しゅんせつ)跡のブレイクライン(かけあがり)、ウィードのアウトサイドエッジ(外側の切れ目)などを、リップで底を叩く(ボトムノック)ように巻いてくるのが基本です。
根掛かり回避性能が高いモデルを選び、ボトムの感触をロッドで感じながらリトリーブ(巻き取り)するのが釣果アップのコツです。
潜行深度別に1m潜るシャロークランクから5m以上潜るディープクランクまで用意しておくと、様々な状況に対応できます。
| おすすめルアー | 特徴 | 推奨潜行深度/カラー例 |
|---|---|---|
| エバーグリーン ワイルドハンチ | 高い障害物回避性能と安定したアクション | 1.2m/チャート系、クローフィッシュ系 |
| ノリーズ ショットオーバーシリーズ | 潜行深度別にラインナップ、優れた飛距離 | 2m~5m/ボーン、ブルーバックチャート |
| メガバス DEEP-X 300 | 急潜行能力と低重心設計による安定アクション | 5m/セクシーシャッド、和銀ハス |
ただ巻きだけでなく、リトリーブスピードに変化をつけたり、ストップ&ゴーを入れたりすることで、より多くのバイトチャンスを作り出せます。
食わせの定番 ネコリグ
ネコリグは、ストレートワームの頭付近にネイルシンカー(細長い重り)を挿入し、ワームの中央付近にマス針をワッキー掛け(横からチョンと刺す)するリグ(仕掛け)です。
非常にシンプルですが、その食わせ能力は抜群で、タフな状況を打開する切り札となります。
アクションは、ボトム(湖底)まで沈めてから、ゆっくりとズル引いたり、ロッドティップ(竿先)を細かく震わせてシェイクしたりするのが基本です。
移動距離を抑えて一点で誘うことができるため、スポーニングベッド(産卵床)にいるバスや、低活性でルアーを追い切れないバスに対して特に有効です。
ネイルシンカーの重さは0.9g~1.8g程度を基準に、水深や流れ、バスの反応を見ながら調整します。
| おすすめワーム | 特徴 | 推奨カラー例 |
|---|---|---|
| O.S.P ドライブクローラー | 自発的なクネクネアクション | グリーンパンプキン、スカッパノン |
| ゲーリーヤマモト カットテール | シンプルながら実績の高い定番ワーム | ウォーターメロン、ブラック |
| ジャッカル フリックシェイク | 独特のカーブ形状による微細な波動 | コーラ、ジュンバグ |
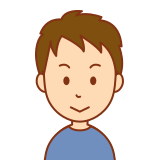
根掛かりしやすい場所ではどうすればいい?

ガード付きのマス針を使ったり、シンカーを軽くしたりすると根掛かりを軽減できますよ
ラインを張りすぎず、少し緩ませた(ラインスラック)状態で操作することで、よりナチュラルな動きを演出しやすくなります。
中層ふわふわ誘い ジグヘッドワッキー
ジグヘッドワッキーは、ワッキー掛けしたワームに、重り付きの針であるジグヘッドを組み合わせたリグです。
ネコリグがボトム中心の釣りなのに対し、ジグヘッドワッキーは中層を漂わせるように誘うのが得意技です。
ロッド操作でリグをフワフワと上下させたり(ミドスト:ミッドストローリング)、ゆっくりと泳がせたり(スイミング)して、バスにアピールします。
ウィードの上っ面や、ブレイクラインの中層など、バスが底から少し浮いている状況で威力を発揮します。
ジグヘッドの重さは0.9g~2.7g程度で、狙いたいレンジやフォールスピードに合わせて選択します。
サイトフィッシング(見えているバスを釣る)にも有効なリグです。
| おすすめワーム | 特徴 | 推奨カラー例 |
|---|---|---|
| ジャッカル フリックシェイク | 微細なバイブレーションと自然なフォール | コーラ、ウォーターメロンペッパー |
| デプス デスアダー | 水平姿勢を保ちやすい形状、強い水押し | スカッパノン、グリーンパンプキン |
| レインズ スワンプクローラー | 多様なリグに対応する万能ストレートワーム | グリーンパンプキン、エビミソ |
フォール中(沈んでいる最中)にバイトが出ることが多いので、ラインの動きに常に注意を払い、わずかな変化も見逃さないようにしましょう。
カバー撃ちの静かな一手 高比重ワーム
高比重ワームとは、ワームの素材自体に塩などの比重が高い物質を多く練り込み、シンカー(重り)を付けなくても十分な自重を持つワームのことです。
ノーシンカーリグで使うのが一般的です。
最大のメリットは、静かにポイントへアプローチできる点です。
着水音が小さいため、アシ際、ウィードの隙間、桟橋の下といったプレッシャーがかかりやすいカバー(障害物)に潜むバスに対して、警戒心を与えずに口を使わせることができます。
キャスト後、ラインを張らず緩めずの状態で自然にフォールさせ、着底後もしばらくステイ(放置)させるのが基本アクションです。
5インチ~6インチクラスが琵琶湖ではよく使われます。
| おすすめワーム | 特徴 | 推奨カラー例 |
|---|---|---|
| ゲーリーヤマモト ヤマセンコー | シンプルイズベスト、圧倒的な実績 | グリーンパンプキン/ブラックフレーク、ブラック |
| デプス カバースキャット | スライドフォールアクションと高いすり抜け性能 | グリーンパンプキン、ブルーギル |
| イマカツ ステルススイマー | ジョイント構造によるリアルなスイムアクション | リアルアユ、琵琶湖ワカサギ |
フックは、根掛かりを回避しやすいオフセットフックを使用するのが一般的です。
バックスライドセッティングも有効です。
おすすめルアーの使い方 アクションの基本
様々なルアーを紹介しましたが、そのポテンシャルを最大限に発揮させるためには、基本的なアクション(動かし方)の理解が不可欠です。
ルアーごとに得意なアクションがあり、それを状況に合わせて使い分けることで釣果は大きく変わります。
主なアクションとしては、ただ巻き、ストップ&ゴー、トゥイッチ、ジャーク、リフト&フォール、シェイク、ズル引きなどが挙げられます。
重要なのは、単一のアクションを繰り返すだけでなく、意図的に動きに変化を加えることです。
例えば、ただ巻きの中に一瞬ストップを入れたり、リフト&フォールのスピードを変えたりすることで、バスの捕食スイッチが入ることが多々あります。
大まかな目安として、約8割は基本に忠実なアクション、残りの約2割で変化球を混ぜるイメージです。
| アクション | 主なルアー | コツ |
|---|---|---|
| ただ巻き | クランクベイト、スピナーベイト | 一定速度で巻く、ルアー本来の動きを引き出す |
| ストップ&ゴー | ミノー、シャッド、クランク | 巻いて止めるを繰り返 |
状況別 4月の琵琶湖ルアー戦略 選び方と釣り方のコツ
- 南湖エリアの攻略法 おかっぱりとウィード
- 北湖エリアの攻略法 ディープとクリアウォーター
- 東岸と西岸 地形に合わせたアプローチ
- おかっぱりで有効なルアー選び
- ボート釣りで試したい攻め方
- ルアーに合わせたタックル選びの基本
4月の琵琶湖でバスを攻略するには、エリアや釣り方といった状況判断に基づいたルアー戦略が非常に重要になります。
広大な琵琶湖は、南湖と北湖で大きく特徴が異なり、さらに東岸・西岸の地形差、おかっぱりかボートかによっても有効なアプローチが変わってきます。
もちろん、選んだルアーに合わせて適切なタックルを用意することも欠かせません。
それぞれの状況に最適なルアー選びと釣り方のコツを掴むことが、春のデカバスへの近道となります。
南湖エリアの攻略法 おかっぱりとウィード
南湖は琵琶湖の南側に位置し、シャロー(浅い水深)が多く、春になるとウィード(水草)が生い茂ることが特徴です。
特に春先に生え揃うウィードの新芽周りは、プリスポーンのバスがベイトフィッシュを捕食したり、スポーニングエリアとして意識したりする重要なポイントです。
おかっぱりから狙える足場の良いポイントも多く、ウィードの種類や密度に合わせたルアー選択が釣果を左右します。
| ルアータイプ | 具体例 | 有効な状況/使い方 |
|---|---|---|
| スピナーベイト | O.S.P ハイピッチャー | ウィードの上や際を効率よく探る、サーチベイトに |
| 高比重ワーム | デプス カバースキャット | ウィードポケットやカバーへの静かなアプローチ |
| ネコリグ | O.S.P ドライブクローラー | ウィードの中やボトム付近を丁寧に誘う |
| シャロークランク | エバーグリーン ワイルドハンチ | ウィードに軽く当てながらリアクションを誘う |
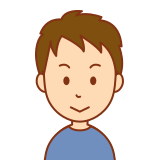
南湖のおかっぱりは根掛かりが心配…

ウィードの種類を見極めて、引っかかりにくいルアーを選ぶのがコツですよ!
ウィードレス性能の高いスピナーベイトや、スナッグレスネコリグ、高比重ワームのノーシンカーなどを中心に、ウィードの中やエッジ(境目)を丁寧に攻めることが、南湖攻略の鍵となります。
北湖エリアの攻略法 ディープとクリアウォーター
琵琶湖の北湖は、南湖と比較してディープ(深い水深)エリアが多く、水質がクリアウォーターであることが特徴です。
春の北湖では、水深10m以上のディープエリアに残っているバスや、産卵のためにディープからシャローへ移動してくるバスを狙うことになります。
クリアウォーターのためバスにルアーを見切られやすく、ナチュラルカラーのルアーや、ロングキャスト(遠投)でプレッシャーを避ける工夫が重要です。
| ルアータイプ | 具体例 | 有効な状況/使い方 |
|---|---|---|
| メタルバイブ | エバーグリーン リトルマックス | ディープエリアのボトム付近でのリフト&フォール |
| サスペンドミノー | メガバス VISION ONETEN | ディープ隣接の岬やハンプ周りでのジャーク&ポーズ |
| ジグヘッドリグ | ジャッカル フリックシェイク | 中層スイミングやボトムでのシェイク(ミドスト、ボトスト) |
| ロングビルミノー | ノリーズ ショットオーバーシリーズ | ディープクランキングで広範囲を探る |
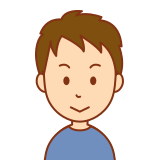
クリアウォーターだと、バスにすぐ見切られそう…

ラインを細くしたり、ルアーから距離を取ったりする工夫が大切です!
飛距離の出るメタルバイブレーションやロングビルミノーでの広範囲サーチ、食わせ能力の高いジグヘッドリグやサスペンドミノーでの丁寧なアプローチを使い分けることで、クリアウォーターの賢いバスを攻略しましょう。
東岸と西岸 地形に合わせたアプローチ
琵琶湖は東岸が比較的遠浅な地形が多く、西岸は急深な地形が多いという違いがあります。
東岸では広大なウィードフラットやサンドバー(砂の堆積地)を広範囲に探る釣りが有効な一方、西岸では急なブレイクライン(水深が急に変わる境目)やロックエリア(岩場)、リップラップ(護岸の石積み)などをピンポイントで狙う釣りが有効になります。
漁港周りなども見逃せないポイントです。
| エリア | 地形の特徴 | 有効なアプローチ例 |
|---|---|---|
| 東岸 | 遠浅、ウィード | バイブレーションやスピナーベイトでの広範囲サーチ |
| 東岸 | 河口、サンドバー | シャッドやミノーでのフィーディング狙い |
| 西岸 | 急深、ブレイク | フットボールジグやメタルバイブでの縦の釣り |
| 西岸 | ロックエリア、漁港 | クランクベイトやテキサスリグでのストラクチャー(障害物)撃ち |
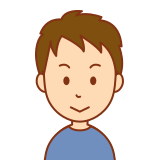
東岸と西岸、どっちに行けばいいか迷う…

その日の風向きや、自分の得意な釣りに合わせて選ぶのがおすすめですよ!
東岸と西岸の地形的な特徴を理解し、風向きや水の流れなども考慮しながら、効率的にポイントを絞り込んでいくことが重要です。
おかっぱりで有効なルアー選び
限られた範囲からアプローチする必要があるおかっぱりでは、飛距離と根掛かり回避性能がルアー選びの重要なポイントになります。
遠投性能に優れたバイブレーションやメタルバイブ、風の影響を受けにくいカバー周りを攻めやすい高比重ノーシンカーワームは、おかっぱりの強い味方です。
また、足元から狙えるウィードエリアや護岸際には、ネコリグやスピナーベイトなども効果を発揮します。
| ルアータイプ | 具体例 | おかっぱりでのメリット/使い方 |
|---|---|---|
| バイブレーション | デプス サーキットバイブ | 遠投性能が高く、広範囲を効率よくサーチできる |
| 高比重ワーム | ゲーリー ヤマセンコー | 飛距離が出やすく、カバー撃ちやスキッピング(水面を跳ねさせる)に有効 |
| スピナーベイト | O.S.P ハイピッチャー | 根掛かりしにくく、ウィードエリアや護岸際を探りやすい |
| シャッド | ジャッカル ソウルシャッド | 足元まできっちり引け、小場所でも丁寧に探れる |
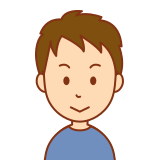
おかっぱりだと、どうしてもルアーの種類が限られちゃう…

大丈夫!少ないルアーでも、使い方次第で十分釣果は伸ばせますよ!
ポイントを移動しながら広範囲を探るランガン(Run & Gun)や、反応を見ながらルアーの種類やカラーを変えるルアーローテーションを意識することで、おかっぱりでも効率よくバスを見つけ出すことができます。
ボート釣りで試したい攻め方
ボート釣り最大のメリットは、機動力とアプローチの自由度の高さです。
おかっぱりからは届かない沖のウィードエリアやブレイクライン、ハンプ(湖底の小山)などを魚群探知機を活用したピンポイント攻略が可能です。
また、風や流れを利用してボートを流しながら広範囲を探るドリフト釣法や、エレキ(電動モーター)を使って静かにポイントへ近づくアプローチも試せます。
| 攻め方 | おすすめルアータイプ | 狙う場所の例 |
|---|---|---|
| ドリフト釣法 | スピナーベイト、クランク | 広大なウィードフラット、シャロー |
| ピンポイント直撃 | フットボールジグ、ヘビダン | 沖のハンプ、漁礁、沈船 |
| ウィードエッジ攻略 | テキサスリグ、パンチング | ウィードの濃いエリアの境目 |
| ディープクランキング | ロングビルミノー | ディープフラット、浚渫跡 |
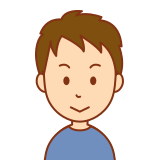
ボートだとどこでも行けるけど、逆にポイントが絞れない…

魚探の情報や過去の釣果データを参考に、狙いを定めていくのが効果的です!
広大な琵琶湖だからこそ、闇雲にキャストするのではなく、魚探やGPSを活用してバスが着きそうなピンスポットを見つけ出し、最適なルアーとアプローチで攻略していくことが、ボート釣りの醍醐味であり釣果への近道です。
ルアーに合わせたタックル選びの基本
ルアーの性能を最大限に引き出すためには、ロッド(竿)、リール、ライン(糸)を組み合わせたタックルバランスが非常に重要です。
軽いルアーを繊細に扱うにはスピニングタックル、重いルアーを遠投したり、カバーからバスを引き離したりするにはベイトタックルが適しています。
ルアーウェイトに合わせたロッドパワー(硬さ)やアクション(調子)、そしてラインの種類(フロロカーボン、ナイロン、PE)と太さを適切に選ぶことが、操作性や感度、フッキング(合わせ)の成功率に繋がります。
| ルアータイプ | 推奨タックル | ロッド例 | ライン例 |
|---|---|---|---|
| ネコリグ、ジグヘッドワッキー | スピニング | L~MLクラス、ソリッドティップ搭載モデル | フロロカーボン 3~5lb |
| ミノー、シャッド | スピニング/ベイト | ML~Mクラス、レギュラーテーパー | フロロカーボン 6~12lb |
| バイブレーション、スピナベ | ベイト | M~MHクラス、レギュラーファーストテーパー | フロロカーボン 12~16lb |
| クランクベイト | ベイト | M~MHクラス、グラスコンポジットロッド | フロロカーボン/ナイロン 12~16lb |
| 高比重ワーム、テキサス | ベイト | MH~Hクラス、ファーストテーパー | フロロカーボン 14~20lb |
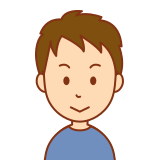
タックルって、結局どれを選べばいいの?

まずは自分がメインで使いたいルアーに合わせて、バランスの良い1本を選ぶのがおすすめです!
高価なタックルである必要はありませんが、ルアーの重さや特性に合ったタックルを選ぶことで、ルアー本来のアクションを出しやすくなり、バスからの繊細なアタリ(魚信)を感じ取りやすくなります。
快適に釣りを続けるためにも、タックルバランスは意識しましょう。
春の琵琶湖を制覇 次の釣行でデカバスを狙う準備
4月の琵琶湖でデカバスやランカーバスを狙う上で、ルアー選択と同じくらい、いや、それ以上に周到な準備が釣果を大きく左右します。
ただ闇雲にルアーを投げるのではなく、スポーニング期の心構えを持ち、状況に応じたルアーローテーションを考え、情報収集を怠らず、そして安全対策を万全にすることが重要になります。
これらの準備をしっかり行うことで、戦略的にデカバスに近づくことが可能です。
スポーニング期攻略の心構え
スポーニング期とは、バスが産卵する時期のことです。
この時期のバスの行動を理解することが、琵琶湖のバス釣り攻略の第一歩となります。
4月の琵琶湖では、プリスポーン(産卵前)で浅場に移動し体力を蓄えるバス、ミッドスポーン(産卵中)で産卵床を守るオスバス、ポストスポーン(産卵後)で体力を回復させようとするバスなど、様々な状態のバスが混在します。
特に産卵床を守るバスに対しては、過度なプレッシャーを与えず、敬意を払う姿勢が大切になります。
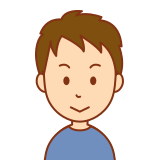
スポーニング期のバスって、なんだか釣りにくいイメージがあるな…

時期によってバスの状態は大きく変わります。その状態に合わせたアプローチを心がけるのがコツですよ
バスの生態を理解し、適切な距離感でアプローチすることが、結果的に釣果へと繋がるのです。
ルアーローテーションの考え方
その日の状況に合わせてルアーを使い分ける、ルアーローテーションは、4月の琵琶湖攻略に不可欠な戦略です。
天候(晴れ、曇り、雨、風)、水温、水の濁り具合、時間帯、そしてバスの反応を見ながら、ルアーのタイプ、カラー、サイズ、アクションを変えていく必要があります。
例えば、朝マズメの活性が高い時間帯はスピナーベイトやバイブレーションで広範囲を探り、反応が鈍くなったらサスペンドミノーのジャーク&ポーズや、ネコリグ、ジグヘッドワッキーといった食わせの釣りに切り替える、といった具合です。
最低でも3種類以上の異なるルアータイプを用意し、積極的にローテーションを試しましょう。
| 状況 | ローテーションの方向性 | 具体的なルアー例 |
|---|---|---|
| 朝マズメ・高活性 | 広範囲サーチ・アピール重視 | スピナーベイト、バイブレーション、クランクベイト |
| 日中・低活性 | 食わせ重視・スローな誘い | ネコリグ、ジグヘッドワッキー、サスペンドミノー |
| クリアウォーター | ナチュラルカラー・フィネス | ワカサギカラーのミノー、シャッド、小型ワーム |
| 濁り・ローライト | アピールカラー・波動重視 | チャート系クランク、ブラック系スピナーベイト |
| ウィードエリア | すり抜け性能・ウィード攻略 | スピナーベイト、テキサスリグ、高比重ワーム |
| バスが追うが見切る | サイズダウン、カラーチェンジ、アクション変更 | 小型ミノー、同系色だが違うカラー、ポーズ時間を長く |
固定観念にとらわれず、状況に応じてルアーを交換していく柔軟な思考が釣果アップの鍵となります。
釣果アップのための情報収集術
琵琶湖での釣果を上げるためには、最新かつ信頼性の高い情報を集めることが非常に大切です。
特に広大な琵琶湖では、エリアによって状況が大きく異なることが多々あります。
釣行前には、直近の釣果情報、ヒットルアー、釣れているエリア(南湖、北湖、東岸、西岸など)、水温の変化、ウィードの生育状況などをチェックしましょう。
信頼できる情報源としては、琵琶湖を専門とするフィッシングガイドのウェブサイトやSNS、地元の釣具店のブログや釣果レポート、気象情報サイトなどが挙げられます。
友人や釣り仲間とのリアルタイムな情報交換も有効です。
| 情報収集源 | チェックするポイント |
|---|---|
| 琵琶湖専門ガイドのブログ/SNS | 最新釣果、ヒットルアー、エリア、パターン |
| 釣具店の釣果情報 | 地域ごとの釣果、売れ筋ルアー、スタッフ推奨情報 |
| 気象情報サイト | 天気予報、風向き・風速、水温データ |
| 琵琶湖関連ウェブサイト/アプリ | 湖の水位、放水量、ウィードマップ(提供があれば) |
| 釣り仲間との情報交換 | リアルタイムな状況、現場の雰囲気 |
複数の情報源から多角的に情報を集め、それらを分析して自分の釣りのプランに落とし込むことが、釣果への近道です。
安全に楽しむための注意点
何よりも大切なのは、安全に釣りを楽しむことです。
琵琶湖は日本最大の湖であり、天候が急変することも少なくありません。
釣行前には必ず天気予報(特に風向きと風速、波の高さ)を確認し、無理な釣行は避けましょう。
ボート釣りはもちろん、おかっぱりでもライフジャケットを必ず着用します。
足場の悪い場所や濡れた場所での転倒を防ぐため、滑りにくい靴を選びます。
日差し対策の帽子や偏光サングラスも必須アイテムです。
また、漁業関係者や他のアングラーへの配慮、釣り禁止エリアへの立ち入り禁止、ゴミの持ち帰りといった基本的なルールとマナーを守ることが重要です。
| 安全対策項目 | 具体的な内容 |
|---|---|
| 天候チェック | 釣行前の天気予報(風、波)、急変への注意 |
| ライフジャケット | 常時着用(ボート・おかっぱり問わず) |
| 足元の安全 | 滑りにくい靴の着用 |
| 熱中症・紫外線対策 | 帽子、サングラス、水分補給 |
| 緊急連絡手段 | 携帯電話の防水対策と充電 |
| ルールとマナーの遵守 | 釣り禁止エリアの確認、先行者への配慮、ゴミ拾い |
事前の準備と当日の注意を怠らず、安全管理を徹底することで、安心して琵琶湖でのバス釣りを目一杯楽しむことができるでしょう。
よくある質問(FAQ)
- Q4月の琵琶湖バス釣りで、ルアーのカラー選びで特に重視すべき点は何ですか?
- A
4月の琵琶湖では、水の透明度と天候に合わせたカラー選びが重要です。
クリアウォーターや晴天時にはワカサギやアユといったナチュラル系が基本となります。
一方、濁りが入ったりローライト(曇りや雨)だったりする状況では、チャート系やブラック系などシルエットがはっきり出るアピール系のカラーが効果を発揮します。
迷った場合は、まずナチュラル系から試すことを推奨します。
- Q琵琶湖のおかっぱりから4月にランカーサイズを狙う場合、どんなルアーやポイント選択が有効でしょう?
- A
琵琶湖のおかっぱりから4月にランカーを狙うには、プリスポーンの大型メスが接岸する可能性のあるポイント選択が鍵です。
具体的には、ウィードの新芽が絡むエリアやハードボトム、ブレイクラインが岸近くにある場所が有望といえます。
ルアーは、遠投性能に優れるバイブレーションで広範囲を探ったり、食わせ能力の高い高比重ワームのノーシンカーをカバー際にアプローチしたりするのが有効でしょう。
チャンスは多くないものの、粘り強く狙う価値はあります。
- Q4月の琵琶湖で有効なワームのリグは、ネコリグやジグヘッドワッキー以外に何がありますか?
- A
4月の琵琶湖で活躍するワームのリグは多様です。
ネコリグやジグヘッドワッキー以外では、ウィードのすり抜け性能が高い「テキサスリグ」や、よりゆっくりとワームをフォールさせられる「フリーリグ」も非常に有効な選択肢となります。
特にスポーニングを意識したバスがカバー周りに潜んでいる状況で効果を発揮します。
これらのリグも試すことで、釣りの幅は広がります。
- Q4月の琵琶湖の水温変化に対して、どのようにルアー選択を調整すれば良いですか?
- A
4月の琵琶湖は水温変化が激しい時期です。
水温上昇傾向でバスの活性が高いと判断できる場合は、バイブレーションやスピナーベイト、クランクベイトなど動きの速いルアーが有効になります。
逆に冷え込みなどで水温が低下し活性が下がった場合は、サスペンドミノーのポーズを長く取ったり、ネコリグやジグヘッドワッキーでスローに誘ったりする展開が効果的です。
水温を意識したルアー選択を心がけましょう。
- Qプリスポーン攻略でミノー以外に試すべき「巻き物ルアー」はありますか?
- A
プリスポーンのバスは積極的にベイトを追うため、ミノー以外にも効果的な巻き物ルアーは多く存在します。
広範囲のウィードエリアを探るならスピナーベイトが定番です。
また、シャロークランクベイトでウィードトップやハードボトムにコンタクトさせるのも有効な戦略となります。
バイブレーションのリフト&フォールもリアクションバイトを誘発しやすいです。
これらの巻き物ルアーを状況に応じて使い分けてください。
- Q4月の琵琶湖東岸と西岸では、攻め方やルアー選択に違いはありますか?
- A
琵琶湖の東岸と西岸では地形が異なるため、4月の攻め方やルアー選択も変わってきます。
遠浅な地形が多い東岸では、スピナーベイトやバイブレーションで広大なウィードフラットを探るのが有効です。
一方、急深な地形が多い西岸では、ブレイクラインやロックエリアをフットボールジグやメタルバイブ、ディープクランクなどで狙うアプローチが中心になります。
それぞれの地形に適したポイントとルアーを選択しましょう。
まとめ
4月の琵琶湖でバス釣りの釣果を上げるには、スポーニング期のバスの行動を理解し、状況に合わせたルアー選択が鍵です。
この記事では、琵琶湖で4月に実績のあるおすすめルアー10選や、南湖・北湖、おかっぱり・ボートといった状況に応じたバス釣りの攻略法、プリスポーン期のバスを狙うコツ、そして釣り方や情報収集、安全対策まで詳しく解説しました。
- スポーニング期のバス行動理解とプリスポーン攻略の重要性
- 状況に応じたルアー(ミノー、バイブレーション、スピナーベイト、ネコリグ、ワーム等)の選択と使い方
- 琵琶湖のエリア(南湖、北湖)や釣り方(おかっぱり、ボート)に合わせた戦略
- 最新情報収集と安全対策の徹底
このガイドを参考に、あなたに合った4月の琵琶湖でのバス釣り戦略を練り、効果的なルアーを準備して、春のデカバス攻略に挑戦しましょう。


